ページ番号:263937
掲載日:2025年1月31日
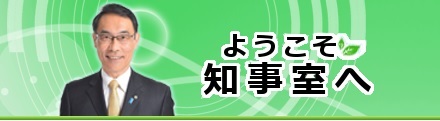
ここから本文です。
東部地域(令和6年10月30日)
訪問日
令和6年10月30日(水曜日)
訪問地域
東部地域(八潮市、草加市)
訪問先
来ハトメ工業 株式会社(八潮市)
2010年9月に環境省の認証登録制度「エコアクション21」の認証を取得して以来、地道に環境に配慮した経営を続けている企業です。
注目すべきは、15年にわたり社内で年間40回の環境教育を続け、社員全員が環境やSDGsの取組を「自分ごと」と捉えて実践している点です。省エネ診断の専門家の助言を取り入れ、継続的な環境教育と全社員による省エネの取組により、従来比97%のCO2排出量削減を約8年で達成しました。
その成果の一つとして、環境コミュニケーション大賞(環境省主催)の環境経営レポート部門で殿堂入りを果たすなど、中小企業における脱炭素経営で注目を集めています。
さらに、「環境人づくり企業大賞」のほか「脱炭素チャレンジカップ2023」では環境大臣賞グランプリなど、環境分野において数々の賞を受賞しています。
訪問先では、製造ラインなど工場の見学と代表者及び従業員と意見交換を行いました。
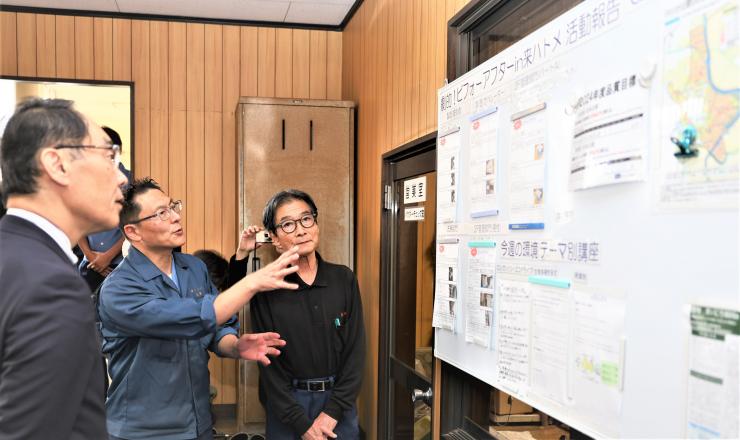
環境教育の一環として掲示されたレポートの説明を受ける
知事
最初は「コスト削減」から始まったと伺いました。コスト削減と環境改善は、どの企業も取り組んでいますが、貴社がここまで成果を出せているということは、他企業と大きな差があるように思います。つまりどこかで、環境優先に大きくハンドルを切られたのだろうと思いますが、どのようなきっかけがあったのでしょうか。
来代表取締役社長
環境問題に背を向けていたならば、当然企業としては成り立たたず、我が社の製品はまずお客様に買っていただけなくなるのではと予想しました。 私はあまりそういった知識はなかったのですが、石原課長が環境問題に対して非常に高い意識を持っていました。彼をリーダーに指名してから、徐々に成果が出てきたことは間違いないと思います。最初のきっかけは、環境問題に関心のない会社は取り残されるという危機感です。
石原管理部課長
私も実は、学生時代に環境について学んだわけではなく、完全に素人からのスタートでした。会社が「エコアクション21」を取得することになり、責任者を任され、社内調整や勉強をいろいろしました。そうした中で、環境コミュニケーション大賞という表彰制度があることを知りました。自分たちで工夫を繰り返しているうちに、3年で大賞を取ることができ、最終的に8回受賞という評価をいただきました。従業員としても「評価されている会社に勤めているんだ」という意識が生まれたことで、社内全体の雰囲気が変わり、大きく環境の方に舵を切れたのだと思っています。
知事
コスト面、お金の部分でも随分苦労されているのではないでしょうか。どの企業に伺っても「環境に良い方が良いですよね」と言いますが、「これだけのコストがかかります」という話をすると皆さん尻込みしてしまう。環境に力を入れることによってもちろんコストはかかりますが、それなりの付加価値が出れば利益につなげることもできます。その辺のバランスというのはどのように考えていますか。
来代表取締役社長
環境に良いことの評価はなかなかコストへ反映できないのが現状です。非常に辛いところですが、もう100%近くまでCO2の削減ができているわけですから、あとはやるべきことを粛々とやっていく、それしかないと考えています。
知事
我々は、価格転嫁を一生懸命推進しています。価格転嫁に関する支援ツールがあり、日本でも埼玉だけのものがありますので、是非、活用してください。
KOTOBUKI Medical 株式会社
「手術トレーニング用品といえばKOTOBUKI」と、世界中で通用する未来を目指しているベンチャー企業です。
この企業は、4年間にわたり1000回以上の試作を行い、外科医療分野の複数のプロフェッショナルによる度重なる品質評価プロセスを経て、コンニャク粉を主成分とした手術トレーニング用模擬臓器、VTT(Versatile Training Tissue)を開発しました。
この模擬臓器は、切開や縫合などの感覚のリアリティを追求し、その特許技術により、世界の高度医療機器メーカーと取引を展開しています。従来の豚などの生体臓器と比較して衛生面に優れ、長期保存も可能な模擬臓器は、多くの優位性があります。
日本のみならず欧州、米国においても特許を取得し、人体組織に非常に近いリアルな感触が評価され、市場が拡大しています。
また、多機能型腹腔鏡トレーナーなどの手技練習用機器の製造により、手術力の向上に向けて個人で研鑽できる環境づくりに貢献しています。
訪問先では、手技練習用機器の体験や模擬臓器の製造工程の見学と代表者及び役員との意見交換を行いました。

腹腔鏡手術トレーニング機器を体験する
知事
拝見させていただいて、模擬臓器がとてもリアルだと感じました。BtoB(企業間取引)がほとんどであるとのことですが、直接取引した方が、利益が上がるのではないかと率直に感じました。その点についてお聞かせください。
高山代表取締役
企業が購入してくれていますが、転売しているわけではありません。企業が新しい超音波メスや新しいデバイスを医師たちに紹介する際に、私たちの製品を使うことでリアルな感触を提供できるようになっています。現状では、医療機器メーカーが製品を購入して消費するという流れです。
知事
同じ時に使うわけではないので単純比較は難しいかと思いますが、生体とPVAと御社のVTTと価格的な競争力はどうなのでしょうか。
高山代表取締役
生体に関しては、豚1頭は、5万円か7万円程で買えて安いのですが、麻酔が必要になるので獣医を手配しなければなりません。豚1頭使うと50万円以上かかると聞いています。私達の製品は、数千円から数万円で、それ以外に準備が必要ないので、生体と比べるとコストが安いと思います。私達は後発組なので、コストを意識してやっています。
知事
BtoB(企業間取引)でたくさん買うとなると、メーカーは、経済性を求めてくると思いますが、その辺りのマーケティングはどうですか。
梅本取締役営業本部長
幸いにも、メーカーから弊社の技術力を高く評価していただいています。
高山代表取締役
こちらで新製品を作ってメーカーへ買っていただくというより、メーカーのご要望を伺って実際に製品にする、というようなカスタマイズ品がほとんどです。お客様の要望にきちんと応えられる技術力が私たちには備わってきていると思います。
つなぐば家守舎 株式会社
「仕事につながる・母親とつながる・地域につながる」をコンセプトに、様々な人々が参加する地域に根ざしたコミュニティ拠点を展開しています。この拠点は、築30年以上の廃アパートを自分たちでリノベーションしたもので、「ほしい暮らしは私たちでつくる=DIO」をミッションに、子育てしながら無理せず得意なことを仕事にしたいという母親のニーズに対応した運営を行っています。(DIO:Do It Ourselves)
シェアアトリエを一緒に運営するパートナーには、それぞれのライフスタイルに対応できるよう、ルーム型、デスク型、キッチンカフェ型など様々な契約形態を用意しています。
ルーム型の一つとして、NPO法人やさしいくらし企画が「ちいさな木のおへや」を常設し、子どもと一緒にお母さんが交流できる、ほっとできる場所を提供しています。デスク型のコワーキングスペースでは、ライターやカメラマン、デザイナーなど異業種のパートナーが集うことで、新しい仕事の創出や業務が拡大しています。
加えて、地元のお店をメインとしたマルシェ「つなぐ八市(ばいち)」は、定期開催することで、コミュニティの形成と地域活性化に貢献しています。
また、ひと箱本棚のオーナーを募り、その本を貸出しする地域の人がつながる図書館「さいかちどブンコ」は、オーナーが自主的にイベントを開催するなど、文化発信拠点としても親しまれています。(さいかちどブンコ:ブンコの場所がかつて槐戸村(さいかちどむら)だったことから命名)
訪問先では、リノベーションした施設や「さいかちどブンコ」を見学し、代表者や運営に参加するパートナーと意見交換を行いました。

リノベーションした施設における活動の説明を受ける
知事
すごく面白いと思ったのは、デベロッパー、タウンプランニング、アーキテクト、デザイナーなど、いろんな要素を取り入れていることです。エリアは小さいかもしれませんが、全てをやるのはものすごく野心的だと思います。また、そこかしこにアーキテクトとデザイナーの香りがしているのが、すごくプラスの要素だと思います。最初から「まちを作る」という発想は、簡単なことではなかったと思いますし、しかも、バラエティに富んだことをやるとなると、相当なチャレンジだったと思いますがどうですか。
小嶋代表取締役
もちろん、大きなチャレンジだと思って始めました。私が建築士で、彼女がデザイナーです。良い空間があってもやはり、そこに魅力がないと足を運ぶきっかけになりません。空間づくりは私達の得意分野ですが、私たち二人だけでは成し得ませんでした。今日ここにいるパートナーの皆さんの協力があってこそできたのだと感じています。少しずつ集まってきた仲間たちと一緒に仕組みを作り、地域にどんな効果をもたらすかを考え、その先の未来を描きながら活動しています。結果、「まちづくり」と呼ばれていますが、私達は一人一人の暮らしを作ることが、まちづくりに繋がっていると思っています。
知事
マーケットは魅力のあるところに集まります。来たいと思う人たちがいるからこそ、そこに店を出そうと思う人たちが出てくるのだと思います。バラエティに富んでいて素晴らしいと思いました。参加している方をどのように呼び込んでいるのですか。
松村取締役(副代表)
口コミです。大々的に募集するわけではなく、身近な人から広がっていく形です。誰かが小さくやっているのを見て、自分も出店できるかもしれないと感じて参加する人が増えています。
知事
鈴木さんの「小さな木のおへや」は、初期投資が他の方より高く、最初のハードルが高かったと思いますがどうでしたか。
鈴木パートナー(NPO法人やさしいくらし企画代表理事)
私は、第二の人生として新しいチャレンジをしたいという思いで退職し、退職金を初期投資に充てました。支援センターができて、子どもたちやお母さんの行く場所は増えましたが、お母さんたちの精神的な不安は消えていないと問題意識を持っていましたし、不登校や自殺の問題があるため、お母さんたちに寄り添いたいと思っていました。ここは狭いスペースですが、その分お母さんたちとの距離が近く、精神的に寄り添うことができています。初期投資もありましたし、私はボランティアで活動し、スタッフもボランティアです。家賃を払うのが精一杯ですが、それでも毎日が楽しくて幸せです。
知事
実は埼玉県は比較的子どもの居場所が多く、ネットワークも日本一大きいです。子どもの居場所づくりの効果は、貧困でご飯が食べられない子どもに対してだけではなく、孤立しているお母さんにも広がります。お母さんたちにとってもかけがえのない場所になる可能性があると思っています。